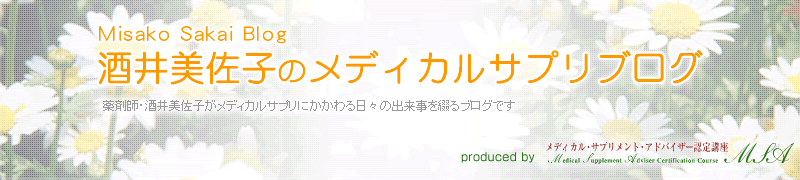2010年ごろから、世界中で、注目されているビタミンがあります。それは、「ビタミンD」です。
2010年に、「認知症とビタミンD」「うつ病とビタミンD」「乳がんとビタミンD」「膀胱がんとビタミンD」「大腸線種とビタミンD」など、多くの論文が発表されました。
上記の疾病の人は、血中のビタミンD濃度が低いことがわかり、たちまち注目されたのです。
血中のビタミンDの濃度は、「血中25-OH-D値」として検査ができますが、残念ながら自己負担になります。
日本の正常基準値は15~40ng/mlとなっていますが、世界的には、値が30 ng/ml未満では不十分、20 ng/ml未満で欠乏症、10ng/ml未満で重度欠乏症と判断されます。つまり、30 ng/ml以上の血中濃度が望ましいとされています。
この、「血中25-OH-D値」は、文献によって単位が異なることに注目ください。
日本では、「ng/ml」が使われますが、海外では「nmol/L」となっていることがあります。
「30 ng/ml」=「75nmol/L」ですので、注意しながら文献を読むことにしています。
ビタミンDはサバ、サケ、イワシなどの食事由来以外に、紫外線、つまり日光浴によって皮膚で合成されます。
皮膚での合成量は、紫外線暴露量に関係するため、血中ビタミンDは季節性の変動があります。2011年に日本人の疫学調査が発表され、日本人の潜在的ビタミンD不足が明らかになりました。オフィスワーカーのビタミンD欠乏の割合は7月が9.3%、11月46.7%と日光に当たらなくなるほど、ビタミンD欠乏がみられたのです。
つまり、秋から冬にかけては、半数の人がビタミンD不足で、補充が不可欠ということになります。
疾病とビタミンDの関係がわかりつつあることから、アメリカでは新しいビタミンD推奨摂取量が改訂されました。
1~70歳 600IU(15μg)、70歳以上 800IU(20μg)、上限が4000IU(100μg)です。
一方、日本人の摂取基準は15歳以上で200IU(5μg)、上限が2000IU(50μg)とかなりの差がみられます。
昨年の国民健康栄養調査では、平均摂取量は280 IU(7μg)でしたので、十分摂取されていると国内では思われています。
ビタミンDと言えば、カルシウムやリンの吸収を促進して骨を健康に保つ、骨の形成に必要なビタミンで、骨粗鬆症の治療や予防で使われていましたが、
今や、免疫調整作用や抗がん作用、インフルエンザ予防作用などが見出され、健康保持や疾病予防のためにビタミンDサプリメントをおよそ1000IU (25μg)摂取することが海外では推奨されています。
ただし、腎障害、高カルシウム血症の方は摂取できませんので、摂取したい場合は、専門家と相談し、可能ならば「血中25(OH)ビタミンD値」をフォローしていきたいものです。