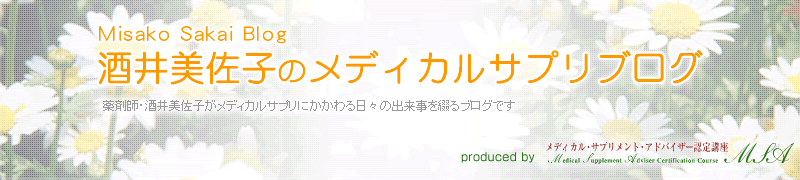9月10日号の健康産業新聞の特集「女性サポートサプリメント」のインタビューを受けました♪
――まず、医療現場でサプリメントやハーブなどを指導する際、留意される点は?
酒井 薬剤師としてサプリメントを推奨するには、「薬との相互作用」、「有効性エビデンスレベル」、「禁忌」、「作用メカニズム」、「副作用」が大きなテーマとになります。このほか、既往歴や各自の遺伝的な体質、食事の摂取状況等を考慮しながらアドバイスを進めます。
――女性特有のPMS(月経前症候群)、生理痛、妊娠などをサポートするサプリメントや素材は?
酒井 イギリスを始めとする欧州ではPMSには伝統的に月見草オイルを勧めます。月見草オイルには不飽和脂肪酸オメガ6のガンマリノレン酸が含まれていて、PMSになりやすい女性はオメガ6濃度が低いと思われているという考えに基づいています。一方、米国では一部で月見草オイルを疑問視する見解もありますが、副作用はごくまれな胃痛以外ほとんどないので、自然療法医が推奨するケースが多く、個人差がありますが試してみる価値はあります。このほかチェストベリー、カルシウムを推奨します。カルシウムはエビデンスもあり体感が早いという声が多いです。
生理痛にはラズベリーリーフというハーブティーが、女性のハーブとして広く利用されます。「産後のお茶」とも言われ、欧州ではPMSでも使用します。
そして「子供がほしい」、つまり妊娠を前提に考えている女性が摂取する方がよいのが葉酸です。周知の通り胎児のためにも1日摂取目安量400㎍以上配合されているマルチビタミンとして摂取することを奨めています。
――更年期障害はどうでしょうか?
酒井 更年期障害としては、大豆イソフラボンが代表格ですが、ポイントは更年期障害なってからでなくそれ以前から、食品を中心に摂取すること。日本人女性は50歳前後が平均的な閉経時期で45~56歳が正常範囲とされていますが、最近は早まる傾向にあります。30代になったら意識して大豆食品を摂取することが大切です。食生活が不規則で、諸事情から大豆食品が摂取できない人の場合は、厚生労働省のいうアグリコン換算で30mgまでならサプリメントで摂取しても構わないでしょう。欧米人に比べて大豆食品を摂取する機会の多い日本人の食生活を前提に考慮した、安全値だと思います。
このほか欧米ではブラックコホシュが使用され日本でも導入されています。医療機関では、血液検査なども考慮し、メディカルサプリメントとして使用されています。
日本人の場合、食生活でのイソフラボン摂取や、人によって代謝酵素の感受性の違いなどがあり、十分考慮して摂取することがすすめられます。
また、女性ホルモン様作用ある素材の摂取は、自分の家系、遺伝に注意することが大切です。母親や自分の姉妹に乳がん患者などのエストロゲン感受性疾患の家系の女性には、食品以外の精製された素材は大量に摂取しないようにアドバイスしています。
――このほか、女性の悩みをサポートする素材は?
酒井 女性は男性より尿道が短いため尿路感染症にかかりやすいのですが、更年期以降は膣内の細菌に対する抵抗力が弱まるなどの理由からさらにリスクが高くなります。同時に若い女性は新婚時に尿路感染症にかかりやすくになります。欧米では利尿系のハーブ、カリウムが入っている西洋タンポポのお茶、クランベリージュースなどが多く利用されます。
このほか女性にとって一番の悩みは便秘です。便秘と下痢を繰り返しているのに何の対処もしないと健康を害すリスクが高まります。さらに高脂肪の食事と砂糖の過剰摂取は要注意です。卵巣がんや乳がんに罹患した人の生活を伺うと、便秘と下痢を繰り返していたのに何の対処もしなかった、仕事が忙しくて生活が不規則、食事を摂らない、高脂肪の食事や糖分の高いデザート、菓子などを多く摂取していた、野菜は取らないケースが多くありました。また、高脂肪食と砂糖やカフェインの過剰摂取はPMSに関係するといいます。食生活の改善、規則生活・食事はもとより、食物繊維や乳酸菌系の食品やサプリ メントの摂取をアドバイスしています。
メントの摂取をアドバイスしています。
と、こんな感じでした。