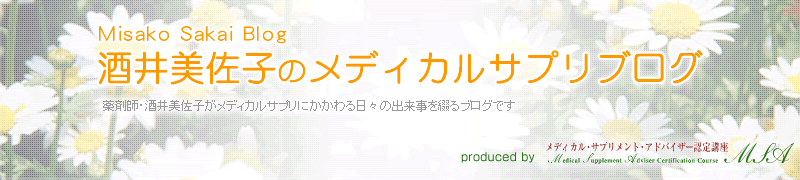梅雨明けかのような日差しが続きます。
6月の薬事法で導入されたOTC薬販売制度がスタートし、ドラッグストアに勤める友人たちは、棚を変えたり、相談口を設置したりと大忙しの1か月だったみたいです。みなさんの職場でも、混乱は少し落ち着きましたでしょうか?
今月7月号の日経DIの特集では、そんな新・薬事法の育て方と題して、薬剤師がどんなことを意識して進めばいいかのヒントがたくさん詰まっていました。また、楽天の三木谷社長の「ネット販売」のインタビューも載っていましたし!
私のほうの連載は、「うつ病」です。セントジョーンズワート、SAMe、DHEAの3つの素材を取り上げています。全国的に心療内科の開業率が上がっているのをみなさん、ご存知でしたか?病院や薬局では、あまりうつ病で休職している人とかはあまりないかと思いますが、企業内では、ほんとに多いそうなんです。春に受けた「心理相談員」研修は、企業の方が多かったので、切実な問題です。
サプリメントで、治る治らないということはさておき、いろいろな症状でサプリメントを使うとき、薬剤師的にEBMが気になるところでしょう。
そこで、改めてEBM(科学的根拠に基づいた医療)について考えてみました。
EBMの手順として、次の5つのstepが提唱されています。
- Step 1 目の前の患者についての問題の定式化
- Step 2 定式化した問題を解決する情報の検索
- Step 3 検索して得られた情報の批判的吟味
- Step 4 批判的吟味した情報の患者への適用
- Step 5 上記1〜4のstepの評価
過去のEBM教育ではこのStep 1〜3が重要視、つまり、どれだけ良い臨床研究を見つけたかが第一だったわけですが、
実は、「Step 4 批判的吟味した情報の患者への適用」、問題の解決に向けて、得られた医学情報のほかに、一般常識や患者の希望を含めて、最良の選択肢を相談することが最も重要ということ。
British Medical Journal のここの論文にあるように、科学的根拠、医師の専門性、患者の価値観の3つからなるもの。
サプリメントに関しては、この科学的根拠(リサーチエビデンス)の円が小さいないまたはないわけですから、他の要素をもって医療を行わなければならないということ。
特に患者さんの価値観には、もっと耳を傾けるべきなんでしょう。
私はそこで、カウンセリング上で2つのことを心がけていることにしました。
「患者さんが持ってきたサプリメントを全否定しないこと」
「サプリメントの基礎知識を教えた上で、患者さんに気づきを与えるようなアドバイスをすること」
もちろん、患者さんが損をする(害になるかもしれない)ようなサプリメントを使っているときは、その理由を説明することで納得してくれますし、薬との相互作用とかは、薬剤師が得意分野とできることなんでしょう。