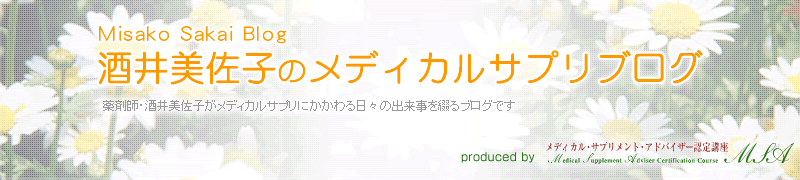東京女子医大の高崎健先生と笠貫宏先生を中心とした創合健康医学研究所主催のセミナーが行われました。
私は、薬剤師・メディカルサプリメントアドバイザーとして参加しました。
「創合医療」とは造語で、西洋医学をベースとして、いろいろな代替療法を組み合わせて具体的に医療の中に組み込むシステムを考えることで、いわゆる統合医療です。
セミナーでは、病気や症状をテーマにして、ケーススタディを話し合い、各代替療法分野の方々と共同研究をしていくことが同意されました。
つまり、臨床心理、音楽療法、アロマセラピー、温熱療法、サプリメント療法などを具体的にどのように評価していくかという共同研究プロジェクトです。
論文にするには、何を指標にするのか、バイアスをかけない方法など必要なので、これからさらに具体化していきそうです♪
今回のセミナーテーマは、「高血圧症」でしたが、早稲田大学人間科学学術院准教授の鈴木伸一先生による「服薬を拒否していた高血圧患者の認知行動療法の介入による症状改善症例」や、東京女子医大循環器内科の桑原和江先生による「メンタルヘルス」の話がありました。
そこで、近年のINTERHEART研究において、心理社会的ストレスは、ほかの危険因子と同様に心筋梗塞の危険因子であることが実証され、臨床上、ストレスが循環器疾患に与える影響が注目されていること、
ストレスの循環器系への作用機序は、
①交感神経‐副腎髄質系の活性による、アドレナリン、ノルエピの放出が、心拍・血圧・発汗・呼吸・筋緊張・血糖↑
②視床下部‐下垂体‐副腎皮質軸(HPA軸)を介する糖質コルチコイド分泌↑による、血圧↑、インスリン抵抗性↑、内臓脂肪肥満型の増悪、ATⅠ受容体の発現増加、コレステロール↑、動脈硬化促進
であること。
また、日常診療におけるうつ病診断のポイントとして、(DSM-IV)
①ここ1か月、毎日のようにほとんど1日中、憂うつだったり、沈んだ気持ちでいましたか?
②ここ1か月、ほとんどのことに興味がなかったり、たいてい、いつもなら楽しめていたことが楽しめなくなったりしていましたか?
このうち一つでも当てはまれば、その後、うつ病の診断問診へとすすむということです。
うつ病の診断は、DSMが診断基準となったようですが、これは、アメリカの診断方法・・・、島国である日本人にはなかなか無理があるような、、、意見もでたりしました。
それより、心身症が世界的には死語になっていることも、驚きです。
病院で、あなたはうつ病です、、なんて言われたら、相当へこみますし、立ち直るのも時間がかかりそう、、、そうなる前に、自然療法での癒しやカウンセリングを、利用してもらいたいものです。
サプリメントとは関係ありませんが、ブランド力について考えてみました。
2008年もポルシェは、アメリカのJ.D.パワー社が実施した「自動車商品魅力度調査(Automotive Performance, Execution and Layout Study)」において、もっとも魅力的で好感の持てるブランドとの評価を得ました。これにより、ポルシェは最大の輸出市場のアメリカで4回連続首位に輝くことになったわけです。
車種別の調査では、911カレラが「プレミアム・スポーティ」部門、ケイマンが「コンパクト・プレミアム・スポーティ」部門、カイエンが「ミッドサイズ・プレミアム・マルチアクティビティ・ビークル」部門でそれぞれ1位を獲得しています。
11日、恵比寿ウエスティンホテルで、恒例の展示会があり、行ってきました。
会場は、さながらパーティーのような感じで、車を鑑賞しながら人々が歓談していました。
高額な車で、注文してから手元にくるまで最低半年はかかるのですが、内装などはすべてオーダーでき、いわゆる自分だけのオーダーメイドカーとなる魅力。
オーナーになってからも、このようなイベントごとにオリジナルグッズをもらえたり、などなど、高級車は多々あるけれども、車を買いました、はい、おしまいというのではなく、買ってからも担当ディーラーさんとのお付き合いは密にあり、イベントごとに言葉をかわし、車というお互いの好きなものに対してとことん、話す。
こんな日々の付き合い方も、ポルシェが車業界で、魅力的な好感のもてる企業であることの一因なのでしょうか
。
今回のイベントも、場の雰囲気や女性限定の「NEW911デビューの記念ケーキ」のサービスなど、心くすぐるサービスに、大変勉強になりました♪

9月10日号の健康産業新聞の特集「女性サポートサプリメント」のインタビューを受けました♪
――まず、医療現場でサプリメントやハーブなどを指導する際、留意される点は?
酒井 薬剤師としてサプリメントを推奨するには、「薬との相互作用」、「有効性エビデンスレベル」、「禁忌」、「作用メカニズム」、「副作用」が大きなテーマとになります。このほか、既往歴や各自の遺伝的な体質、食事の摂取状況等を考慮しながらアドバイスを進めます。
――女性特有のPMS(月経前症候群)、生理痛、妊娠などをサポートするサプリメントや素材は?
酒井 イギリスを始めとする欧州ではPMSには伝統的に月見草オイルを勧めます。月見草オイルには不飽和脂肪酸オメガ6のガンマリノレン酸が含まれていて、PMSになりやすい女性はオメガ6濃度が低いと思われているという考えに基づいています。一方、米国では一部で月見草オイルを疑問視する見解もありますが、副作用はごくまれな胃痛以外ほとんどないので、自然療法医が推奨するケースが多く、個人差がありますが試してみる価値はあります。このほかチェストベリー、カルシウムを推奨します。カルシウムはエビデンスもあり体感が早いという声が多いです。
生理痛にはラズベリーリーフというハーブティーが、女性のハーブとして広く利用されます。「産後のお茶」とも言われ、欧州ではPMSでも使用します。
そして「子供がほしい」、つまり妊娠を前提に考えている女性が摂取する方がよいのが葉酸です。周知の通り胎児のためにも1日摂取目安量400㎍以上配合されているマルチビタミンとして摂取することを奨めています。
――更年期障害はどうでしょうか?
酒井 更年期障害としては、大豆イソフラボンが代表格ですが、ポイントは更年期障害なってからでなくそれ以前から、食品を中心に摂取すること。日本人女性は50歳前後が平均的な閉経時期で45~56歳が正常範囲とされていますが、最近は早まる傾向にあります。30代になったら意識して大豆食品を摂取することが大切です。食生活が不規則で、諸事情から大豆食品が摂取できない人の場合は、厚生労働省のいうアグリコン換算で30mgまでならサプリメントで摂取しても構わないでしょう。欧米人に比べて大豆食品を摂取する機会の多い日本人の食生活を前提に考慮した、安全値だと思います。
このほか欧米ではブラックコホシュが使用され日本でも導入されています。医療機関では、血液検査なども考慮し、メディカルサプリメントとして使用されています。
日本人の場合、食生活でのイソフラボン摂取や、人によって代謝酵素の感受性の違いなどがあり、十分考慮して摂取することがすすめられます。
また、女性ホルモン様作用ある素材の摂取は、自分の家系、遺伝に注意することが大切です。母親や自分の姉妹に乳がん患者などのエストロゲン感受性疾患の家系の女性には、食品以外の精製された素材は大量に摂取しないようにアドバイスしています。
――このほか、女性の悩みをサポートする素材は?
酒井 女性は男性より尿道が短いため尿路感染症にかかりやすいのですが、更年期以降は膣内の細菌に対する抵抗力が弱まるなどの理由からさらにリスクが高くなります。同時に若い女性は新婚時に尿路感染症にかかりやすくになります。欧米では利尿系のハーブ、カリウムが入っている西洋タンポポのお茶、クランベリージュースなどが多く利用されます。
このほか女性にとって一番の悩みは便秘です。便秘と下痢を繰り返しているのに何の対処もしないと健康を害すリスクが高まります。さらに高脂肪の食事と砂糖の過剰摂取は要注意です。卵巣がんや乳がんに罹患した人の生活を伺うと、便秘と下痢を繰り返していたのに何の対処もしなかった、仕事が忙しくて生活が不規則、食事を摂らない、高脂肪の食事や糖分の高いデザート、菓子などを多く摂取していた、野菜は取らないケースが多くありました。また、高脂肪食と砂糖やカフェインの過剰摂取はPMSに関係するといいます。食生活の改善、規則生活・食事はもとより、食物繊維や乳酸菌系の食品やサプリ メントの摂取をアドバイスしています。
メントの摂取をアドバイスしています。
と、こんな感じでした。
がん患者さんの約3割以上が補完代替療法を利用し、5割が関心がある(または準備している)ことが、大阪大学コミュニケーションデザインセンター人間科学研究科医学系研究科の平井先生らの研究から明らかになりました。
また、補完代替療法に最も影響を与えているのは、「家族の期待」です。
癌患者さんのカウンセリングをしていると、サプリメントは特に家族の方が、口コミで聞いてきたものを飲ませているパターンが実に多いのかがわかります。それも、うわさで「癌が治った」と聞いたものを次々と試します。
その行為は、もちろん否定できません。
ただ、気をつけないといけないのは、「患者が嫌々、無理に飲んでいる。食事を減らしてもサプリを飲む」パターン。それから、「治療や症状で、摂取してはいけないサプリがあることを知らない」パターンです。
先週だけでも、肺がん患者さんの「βカロチン高容量」サプリメントの接取、パクリタキセル投与中の「ガーリックサプリメント」の接取、C型肝炎からの肝がん患者さんの「アキウコン高容量」サプリメントの接取に遭遇しました。
エビデンスレベルもありますが、やはりリスクはなるべく避けたいです。。
私が参考にしている、がん情報のサイトです。こちら
米国国立がん研究所(NCI)が配信する包括的がん情報、PDQ®(Physician Data Query) を日本語訳したものです。
アメリカの情報なので、食事のレシピとかは、日本人には合わないと思いますが・・・参考になります!
先日、ビオセラクリニックの院内勉強会で、友人でもあるサイモントン療法認定トレーナーの川畑伸子さんの講演がありました。
サイモントン療法とは、
アメリカの放射線腫瘍医で心理社会腫瘍医の、O.カール.サイモントンが考案した、がん患者とそのサポーター(家族など)のための心理療法です。現在では、がんばかりでなく、心的ストレスを起因とするさまざまな疾病に対して同療法が提供されています。
精神・心理面、感情面が人間の免疫機能に大きな影響を及ぼしていることは認識されていますが、現代医学では、それらの分野はほとんど網羅されていません。
同療法では、人間の本来持っている、バランスをとり自らを健康に導く能力を強化すると同時に、QOLを高めることを目的としているカウンセリング方法です。QOLを低下させる恐怖や苦痛、死に対するとらえ方を変えることも、QOLを高めることにつながります。
サイモントン療法では、「希望」を患者にもたせます。ここでの希望とは、「癌が治るかもしれない」のような憶測なものではなく、「信念」つまり「その人が得たい結果が得られると信じること」を学ぶのです。
そのための段階として、「イメージ療法」「喜び・生きがいワーク」「ビリーフワーク」「イメージの絵」「ストレスパターンと病気の二次的恩恵」「希望・信頼・内なる叡智(Inner Wisdom)・スピリチャリティー」「死生観」「患者のサポートとコミュニケーション」「二年間の健康プラン」とすすんでいきます。
私たち薬剤師は、日々、患者さんと接していて、そのコミュニケーション方法はどうでしょうか?
サイモントン療法の中の「患者のサポートとコミュニケーション」にヒントが見つかります。
ここでは、効果的な真のサポートとコミュニケーションの構築とミスコミュニケーションの解消について取り組むのですが、サポーター(私たち薬剤師も患者さんを支える一種のサポーター)とのかかわりは、癒しの課程に影響を及ぼすといいます。
サポーターの支援が患者にとって、好ましいものであれば、それは癒しの課程にも肯定的な反応をもたらしますが、サポーターが好ましくないものであった場合、それは患者にとってストレスの原因でとなり、病状を悪化させ得ます。サポーターが患者に施したいサポートでなく、患者が受けたいサポートを明確にし、効果的なサポートとコミュニケーションをここでは学びます。
真のサポートとは、患者の得たい結果をサポートする。つまり患者さんが主役なのですね。
薬剤師として、患者が自己判断で、いいと思ってしていることが、その人に悪い結果を及ぼす可能性がある場合、頭ごなしに「そんなことして!!悪化しますよ!」というのではなく、
「あなたの今やっている〇〇〇〇は、あなたのこれからの健康を害していくように見えます。」
「あなたの健康を健全に保つために、△△△△してほしい。」というように信頼を損ねないように。
あくまでも、患者さんが主役で、私たちはサポーターというスタンスを学んだ、そんな勉強会でした♪